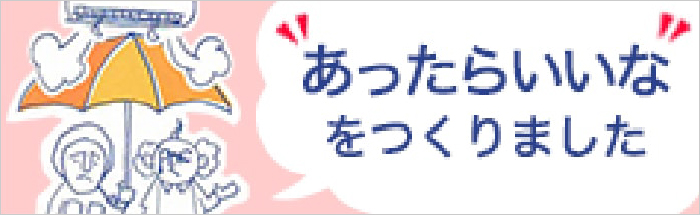村西享一の実家は祖父、父と続く電気工事士、いわゆる職人で、長男の村西は幼いころから家業の跡継ぎになることを期待されていた。
「三代目だね」
小さい頃から、どこに行っても言われる言葉だった。それは村西にとって人生を決められていたようなものだった。 反発したい思いはどこかにあったが、祖父の代から続く家業を自分が潰してしまうわけにはいかないという責任を感じていた。 本来、高校を卒業したら働き始める約束だったが、家業と関連のある専門学校へ行かせて欲しいと懇願した。2年間、思うように生きてみたい。 それが決められた道に対して村西なりの唯一の抵抗だった。村西は高校の頃から始めていたバンドに熱中した。
果たさなければならない責任から一時的にでも解放された日々を送っていた。この時期こそ村西の青春と言ってよかった。 このまま好きな音楽を思いきり続けたいという若者ならではの夢も見た。 しかし、村西は夢を追いかけることはせず、与えられた使命に従うことを選ぶ。
「おい、辞められるものなら、辞めてみろ」
かつて父の顔で入った会社。それを知る先輩からの痛烈な言葉。食事は喉を通らず、胃が痛むほど精神的にも追い込まれる日々が続く。辞める訳にはいかない。 逃げてしまえば父が恥をかくことになるのだ。村西は先輩たちの仕事を観察しながら見よう見まねで必死に喰らいついていく。 出張で多忙を極め、二ヶ月間休暇がないことなど当たり前だった。試行錯誤の日々が続く。 混乱に陥りそうな時でも考えに考えて答えを導き出し、乗り越えながら、職人としての力をつけていく。
この仕事の成果は形として外からまったく見えてこないが、当たり前の結果を残すのみである。 お世話になった会社に対して懸命に仕事をすることで、育てて頂いた恩をお返しした。 十年という修行時代を終え、気がつけば、職人として二十年という歳月を過していた。今は父と二人で仕事をする。 若き日の父も自分と同じように葛藤し、長男として運命を受入れて生きてきたのかもしれない。 「本人には直接言えないけれど、尊敬するしかないですよね」
電気は通って当たり前。スイッチを押すだけで、当たり前に電気はつく。 その配線は、いや、家の神経と言ってもいいだろう。 窮屈な狭いところで、汗まみれになりながら、考えに考えて張り巡らしている。 もしかしたら、こんなこともあるかもしれないと考える。見えない相手を想い、隠れてしまう場所に愛情を注ぐ。
いつか誰かの夢の家が完成する。皆、目に見えるもの、外観の美しさや機能に歓喜し感謝する。 そして、夜になれば「当たり前」に部屋に明かりが灯る。 そこに深く、優しい愛情が込められていることを知る人はいないかもしれない。 だが、家に神経を張り巡らした村西は、心の奥底で独り、こう思うのだ。すべてよし、と。
村西亨一は心の中で、ある言葉を反芻する。習慣と言ってもいい。 時として自分の心に負の感情が沸き上がってきたならば、祈るようにその言葉を何度も自分に言い聞かせる。
「ただ、世界中のすべての人に優しくあれ」
与えられた役目を全うするために。すべてを受け入れ、揺るぎない自分であろうとするために。
(撮影/取材・文 林建次)