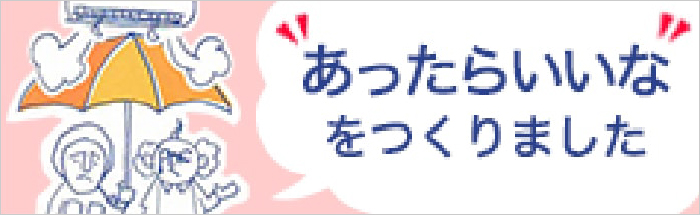十五歳の少年は高校ではなく、左官という仕事を選んだ。
寮に入った齋藤は、家を出られたことに安堵していたが、左官の仕事に興味や向上心はなかった。 蓄積された寂しさを発散するかように、やんちゃな時代を過していた。しかし、十九歳になる頃に転機が訪れる。 齋藤は働いている会社の左官業しか知らず、未だ見習いだった。このままでいいのだろうかと感じ、会社以外の様々な現場を見たいと思うようになった。 そして、外の世界に触れた齋藤は愕然とする。齋藤と同じ年の若き職人たちが、自分よりも遥かに技術は優れていて、責任ある仕事を任されているのだ。 当然、給料も違っていた。明らかに劣っていると認めざるを得ない。しかし、この屈辱が元来負けん気の強い齋藤を本気にさせる。 これ以降、死に物狂いで仕事に取り組んでいった。まだ、上手さも、速さも敵わない。しかし、平米数だけは勝ってやる。そう意気込んで深夜まで独り現場に残り続けた。 無我夢中で仕事に没頭する齋藤は、あらゆることを吸収して飛躍的な進歩を遂げる。二十歳になる前には、年上の職人五人を従える親方として都営住宅の仕事を任せられるまでになった。 家にも帰らずなんとか仕上げたことも、大きな経験となった。
二十五歳の時にコーポラティブハウスの仕事を請け負った。ここで齋藤は塗り壁、漆喰に出会う。 「この仕事にはまってしまった。それまではクロスを貼る下地だったり、ペンキの下地の仕事だったけど、漆喰はそのものが仕上げだから作品に近い。 その分、労力は大きいし、何度も打ち合わせをしなければならないけど、やりがいのあるこの道に進もうと決めたんです」 デリケートな漆喰を扱うのに試行錯誤を繰り返さなければならなかったが、達成した時の充実感はこれまでにないものだった。齋藤は自ら創作する新たな仕事に魅せられた。 以来、ブティックの椅子やカウンターをつくる仕事の依頼も増えていく。困難な仕事も恐れることなく自ら挑戦していく。多くの経験を積みながら、広く、深い左官の世界にのめり込んでいく。 齋藤は下地も、タイルも、漆喰も、木造も、ビルも、左官のすべてのスキルを持った職人の集団を作るために、三十五歳で会社を起こし、今は職人を八人抱えるまでになった。 「下地しかやらない、ビルしか出来ない、と一つのことに特化するのではなく、左官という幅広い領域をカバーしながら、職人としてもっと深く吸収したい。ここに頼めば大丈夫だっていうオールマイティな左官屋ですね」 エアサイクル東京との出会いは2013年夏。左官の世界では神のような存在の植田俊彦の紹介だった。多くの左官職人を見て来た植田は、その中でも齋藤の真剣な姿勢、若き職人の貪欲さを買っていたのだ。
齋藤は、今がもっとも充実していると言い切る。思えば、十五歳で家を出て、やりきれない想いを爆発させるような十代を過した。
しかし、仕事に生きる術を見出してからは、がむしゃらに走り続け、真摯に自分を磨いていった。
そして心の穴を埋めてくれる女性と出会い、結婚して二人の娘の父となり心安らぐ居場所を得た。あの頃になかったものが、今はある。幸せであることに、感謝の気持ちが湧いてくる。
「記憶にない母親だけど、天国からずっと見守ってくれているのかもしれない」
夢中で仕事に打ち込んで結果を出し始めた二十歳の時に、齋藤は母のお墓参りに行った。事実を知った時からずっと会いたいと願っていた。
墓地の住所を聞き出すことはできたが、いくつものお墓が建ち並んでいる敷地のどこに、母が眠っているのかまでは分からなかった。
しかし、自分でも不思議に思うほど、墓地の中を迷うことなく歩き出だしていた。嬉しいのか、悲しいのか、溢れる感情を抑えることが出来ない。
やがて、齋藤は小さなお墓の前に辿り着いた。墓石には母の名が刻まれている。
「お母さん」
この時、齋藤幸洋は一生分の涙を流したのだという。
(撮影/取材・文 林建次)