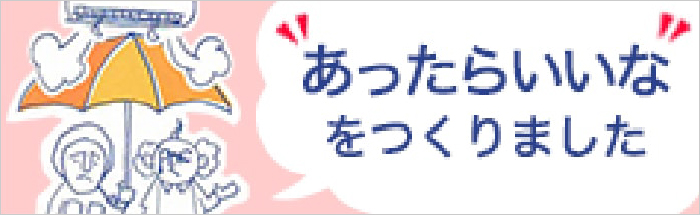照りつける真夏の太陽の下、
十数人の男たちによって小金井の現場で上棟が始まった。
一斉に角材を組み上げてゆく彼らは、息を荒くし、汗まみれになってゆく。 日焼けした二の腕で力強く角材を抱えながら、高垣晃康は高く危険な現場を素早い動作で立ち回っていた。 現場の慌ただしい騒音に消されないよう、大声で後輩の大工たちに指示を出す。 上棟とは、家の骨組みを見事に仕上てゆくダイナミックで華のある、鳶と大工の共同作業。これを終えれば、高垣はただ独り現場に残り、責任を負って家をつくり上げてゆくことになる。 上棟は彼にとって、これから数ヶ月に及ぶ、己との格闘が始まる儀式でもあった。若き大工は孤高に挑んでゆく。
1975年、高垣は埼玉で生まれた。小学校の頃からプロ野球選手を目指してリトルリーグに所属、まるで軍隊のような厳しい環境の中でキャッチャーのポジションを獲得、高校の県大会では3位という好成績も残した。 当然強豪校からの誘いもあったが、高垣は不意にその夢を捨ててしまう。「死に物狂いで頑張っても、他校では涼しい顔をして桁違いのプレーをする奴らが沢山いた。 高校ではそんな彼らとレギュラーを争わなければならない。その時点で圧倒的に抜きん出ていないと、甲子園はおろか、プロなんてとても無理なんです。 自分の実力では敵わないということが分かってしまった。野球で夢見ることはここで終わりました」
高校を卒業した高垣は手に職をつけようと決めて工務店で仕事を始めた。そして初めて行った現場で、いきなり職人の世界の厳しさを見せつけられた。 仕事は分からないことばかりで、ひたすら続く丁稚奉公の日々に、逃げ出したいと思うこともあった。 しかし、五人の同期がいる中で、絶対に負けられないという激しい気概が、彼の心に沸き上がる。 幼い頃からプロ野球選手を目指し、厳しい競争に挑んできた高垣の闘争本能が目覚めた。もう挫折するわけにはいかない。
ここで一番になって、職人として生きてみせる。以後、高垣は徹底した貪欲さを持って、仕事に取り組んでゆく。
時として親方の理不尽なことにも、高垣晃康|大工今は丁稚なのだとじっと堪えて、職人としての力をつけることに集中していった。あの厳しい時代があったからこそ、大工としての自分がある。
そういう意味で高垣は、当時の親方に心から感謝している。
高垣にとって、仕事とはなんだろう。生きるとはなんなのだろう。無意識に語る言葉にこそ、彼の本質が見えて来る。
「幼い頃、休むことなく、ひたすら働き続ける父の記憶が鮮明にある。男とは仕事にすべてを捧げることが当然なのだということを、その背中が語ってくれたように思う」
(職人の貌より一部抜粋 撮影/取材・文 林建次)