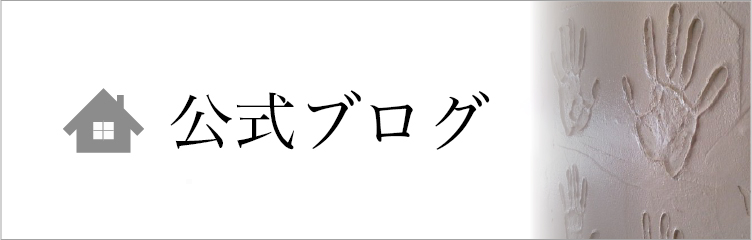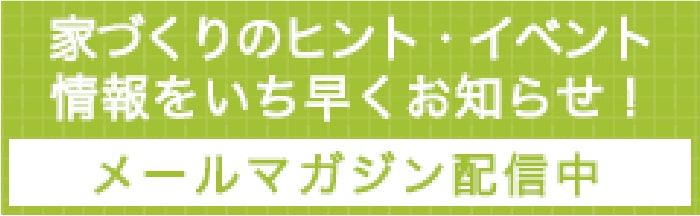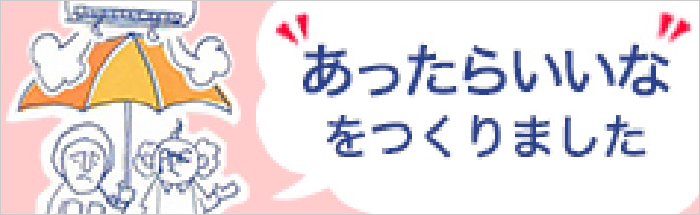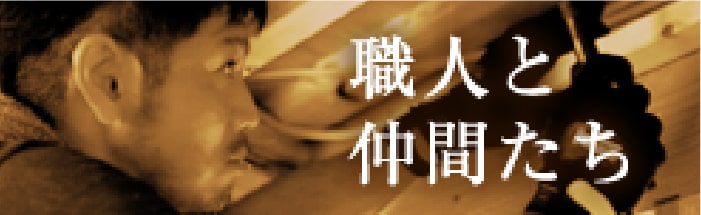地球の恵み「鉄平石」
カテゴリー :家づくりを考える
素材の故郷を探訪する「素材探訪」シリーズ。
今回は「鉄平石」を求めて、長野県諏訪市の藤森鉄平石株式会社の採石場へ行ってきました。
2,400万年の時を経て今あらわれる「鉄平石」
今から約2,400万年前、霧ヶ峰火山のまぐまが冷え固まって鉄平石は誕生しました。長野県諏訪地方を中心に古くから採掘され、 その自然な風合いが建築用の張り石や敷石として珍重されてきました。
「鉄平石が数センチごとに無数の層をなしていること、これが不 思議でならない。神様のしわざとしか説明できませんね。すべては自然がやったこと。」とは藤森鉄平石株式会社の藤森吉三会長の言葉です。

「地球の恵み」そのものの価値とは?
採掘場に着くと、まっぷたつに切った山の断面が目の前に現れ、 その景色と大きさに圧倒されます。
時間をかけて少しずつしみ込んだ水分が錆となり、部分的に赤くなっています。重機を使って、山から岩を切り出し、次に切り出した 岩の塊を作業場まで運び入れます。
地球の恵みをそのままいただくという特性上、どうしても計画的な生産が難しく、それゆえ価格が高くなります。コスパを求める近年は需要が減り、経営状況は厳しいそうです。

地球と会話ができる石工
作業場に運び入れられた岩の塊は、石工が手作業で建材として 使える形状に加工します。石の良し悪し、どこできれいに剥がれるかは、外見から予測をたて、石工の長年の勘を働かせ、ノミを差し込んでいくそうです。
差し込んだノミをハンマーで叩きながら、トントントンと響く音を注意深く聞いていると、微妙に音が変わる瞬間があります。それは石の特性に沿って力が加わり、岩が素直にすんなり剥がれた合図。 石工は、地球と会話しているのかもしれません。

家づくりに使われる材料はどこから来るのか。どんな思いでつくられているのか。
顔の見える材料で、家づくりをしています。